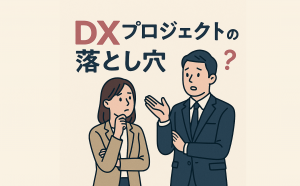DX奮闘記:“原理原則”から始めよう
常識を疑い、ゼロから考える力
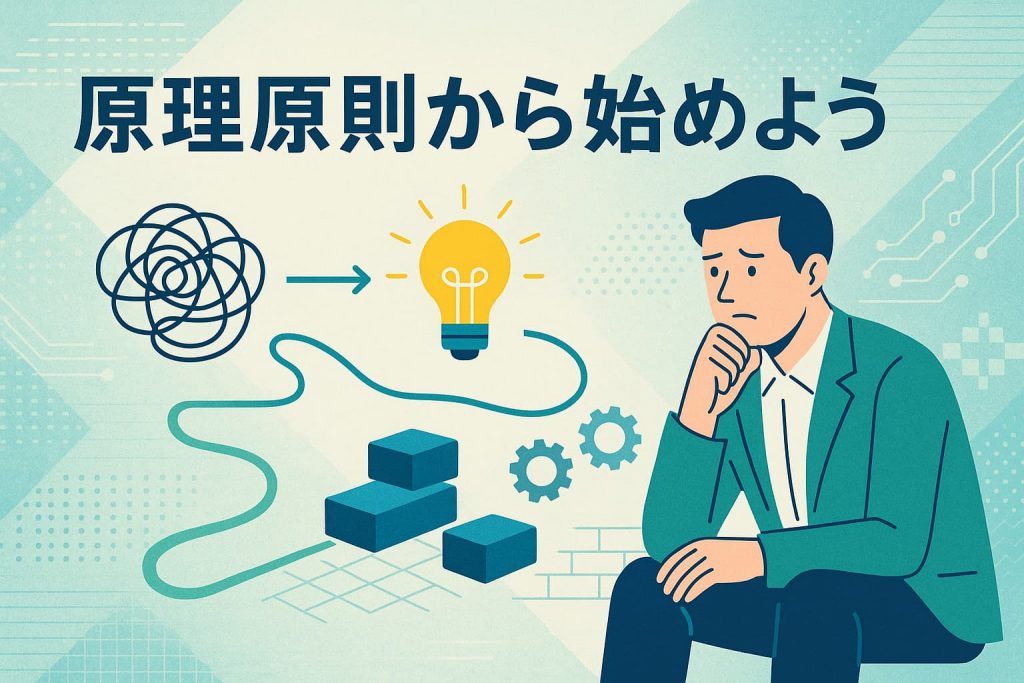
目次
「できる・できない」より大切な問いとは?
新しいプロジェクトや改善提案が持ち上がったとき、皆さんの会社ではどんな声が最初に聞こえてくるでしょうか?
「技術的に難しいのでは?」「社内ルール上できないよね」「コストやリスクが高すぎる」
こうした言葉、きっと多くの方が耳にしたことがあるのではないでしょうか。もちろん、これらの懸念は決して間違いではありません。現実的な制約を考慮することは、ビジネスにおいて重要な要素の一つです。
しかし、問題は「制約ありきの思考」が議論のスタート地点になってしまうことです。まだアイデアの芽が出たばかりなのに、最初から「できない理由」を並べ立ててしまう。これでは、せっかくの可能性が花開く前に摘み取られてしまいます。
私たちがDXに取り組む中で大切にしなければならないのは、まず「できる・できない」といったあらゆるしがらみを一度取っ払って考えることです。そして最初に向き合うのは、こんな問いです。
「原理原則に沿うことは何か?」
例えば、会社の製造工程で何らかの課題が発生したとします。従来の考え方なら「過去の経験では○○だった」「業界の常識として△△は無理」といった前例や慣習から判断しがちです。でも、ちょっと待ってください。その「常識」は本当に絶対的なものでしょうか?
原理原則から考えるということは、問題を最も基本的な要素まで分解し、本当に変えることのできない「真実」だけを出発点にすることです。そこから「あるべき姿」を描いてみる。すると、これまで見えなかった解決策の道筋が見えてくることがあります。
もちろん、原理原則を描いた後で現実的な制約と向き合う時間も必要です。予算、技術、人材、時間─これらすべてを無視していいわけではありません。ただし、それは「あるべき姿」をしっかりと描いてからの話です。
「できる・できない」「現実的には~」という内容を、議論の一番最初から持ち出すことはとてももったいないことです。制約を理由に諦めていたアイデアの中に、実は画期的な解決策の種が眠っていたことに気づくケースも少なくありません。
もちろん、長年培われてきた業界の知恵や社内のルールには、それぞれに意味があります。しかし、時代が変わり、技術が進歩する中で、その「意味」自体を見直すタイミングが来ているのかもしれません。
イーロン・マスクに学ぶ“ゼロからの発想法”
「なぜロケットはこんなに高いんだ?」──宇宙事業への参入を考えていたイーロン・マスクが抱いた、とてもシンプルな疑問でした。当時、ロケット1機の価格は数十億円が当たり前。業界の常識では「宇宙開発にはそれだけのコストがかかるもの」とされていました。
しかしマスクは、この常識を疑うことから始めました。ロケットを構成する材料──アルミニウム、チタン、銅、カーボンファイバーなど──これらの原材料費を計算してみたのです。すると驚くことに、材料費はロケット販売価格のたった2%程度しかありませんでした。
「物理法則に反することは何もないはずだ」
これが、イーロン・マスクが実践するFirst Principles Thinking(第一原理思考)の核心です。アリストテレスの時代から受け継がれてきたこの思考法は、複雑な問題を最も基本的な要素まで分解し、そこから新たに組み立て直すアプローチです。
この発想法のポイントは「なぜ?」を繰り返すことにあります。マスクの場合なら「なぜロケットは高いのか?」「なぜ製造コストがかかるのか?」「なぜ再利用できないのか?」と問い続けました。そして最終的に「ロケットを部品から自社で製造し、再利用可能にすれば大幅なコスト削減ができる」という結論にたどり着いたのです。
私たちも日々の業務で、つい「これは業界のルールだから」「前例がないから難しい」「予算的に厳しい」といった制約ありきで考えてしまいがちです。でも、そうした思い込みが本当に絶対的な制約なのでしょうか?
「できる・できない」という制約から入ると、どうしても場当たり的な対処になりがちです。つぎはぎの対処法を重ねていくうちに、いつかはひずみが生まれて、後から建て直すのがとても大変になってしまいます。実際、いま会社でもそういう状況に直面しています。
だからこそ、DXの担当として、こう自問するようにしています。
「原理原則は何か?」「物理法則に則ったシンプルな解決策は何か?」
先入観や慣習を一度脇に置いて、本質的に「どうあるべきか」から考え直してみる。そこにイノベーションの種が隠れているのかもしれません。
未来を変えるのは、小さな“原理原則”の一歩
第一原理思考について考えるとき、よく混同されがちなのが「理想を描くこと」との違いです。一見すると似ているように思えますが、実は大きな違いがあります。
理想を描くというのは、私たちの願望や希望が含まれがちです。
「こうなったらいいな」「こんなふうになってほしい」という気持ちから出発するものです。
もちろん、それ自体は素晴らしいことですが、時としてその理想が原理原則に反していることもあります。
一方で、第一原理思考で導き出されるのは「最もあるべき姿」です。これは「こうあってほしい」という願望ではなく、「こうあるのが最も理にかなっている」という客観的な答えです。物理法則や基本的な真理に基づいて、最もシンプルで効率的な状態を見つけ出すことなのです。
この思考法のコツは、いろいろなしがらみとなる考えを一度すべて捨てて、とことんシンプルに考えていくことです。
「予算がないから」「前例がないから」「上司が反対するから」といった制約を一旦すべて横に置いて、純粋に「何が最も合理的か」だけを考えるのです。
例えば、何かに取り組んでいて「これはできないな」と思ったとき、立ち止まって自分に問いかけてみてください。
「それは物理法則に反しているから不可能なことなのか? それとも、ただ単に慣習や思い込みによって『できない』と感じているだけなのか?」
実は、私たちが「不可能」だと思っていることの多くは、物理的に不可能なわけではありません。重力に逆らって空を飛ぼうとするような、文字通り物理法則に反することは確かに不可能です。
しかし、多くの場合は「今までそうしてこなかったから」「リスクが高そうだから」「複雑そうだから」といった理由で諦めているだけなのです。
原理原則から一歩ずつ積み上げていくと、意外にもシンプルな解決策が見えてくることがあります。複雑に見えていた問題も、実は基本的な要素の組み合わせだったりするのです。
そして、その基本的な要素一つひとつは、決して不可能なものではないことに気づくはずです。
未来を動かすのは、こうした「原理原則からの一歩」の積み重ねなのです。大きな変革も、最初は小さな気づきから始まります。既成概念を疑い、本質を見つめ、そこから新しい可能性を見出していく。
この繰り返しが、やがて大きな変化を生み出していくのです。
伝統×DX=廣瀬製紙の未来地図
廣瀬製紙では現在、本気でDX化に取り組んでいます。私たちは長い歴史の中で、尊敬すべき先人たちが積み上げてきたすばらしい技術と智恵を大切に受け継いできました。
和紙の製法を用いた湿式不織布という独自の技術も、そうした伝統の延長線上にあります。
しかし、これからの時代を生き抜くためには、その貴重な財産を活かしながらも、建て直していくところは思い切って建て直していく必要があります。
それはまるで、複雑にからまった糸をひとつひとつ丁寧にほどいて、すっきりと整理していく作業のようなものです。
長年の間に積み重なった業務プロセスや仕組みの中には、当時は最適だったものの、今となっては複雑すぎて効率を妨げているものもあります。
そうした部分を第一原理思考で見直し、「本来はどうあるべきか」から考え直すことで、シンプルで本質的な解決策を見つけることができるのです。
私たちDX担当チームは、最新のデジタル技術を積極的に取り入れながらも、常に「物理法則に則った、できる限りシンプルな解を導く」ことを心がけて活動しています。
伝統と革新のバランスを保ちながら、廣瀬製紙の未来を切り開いていきたいと考えています。