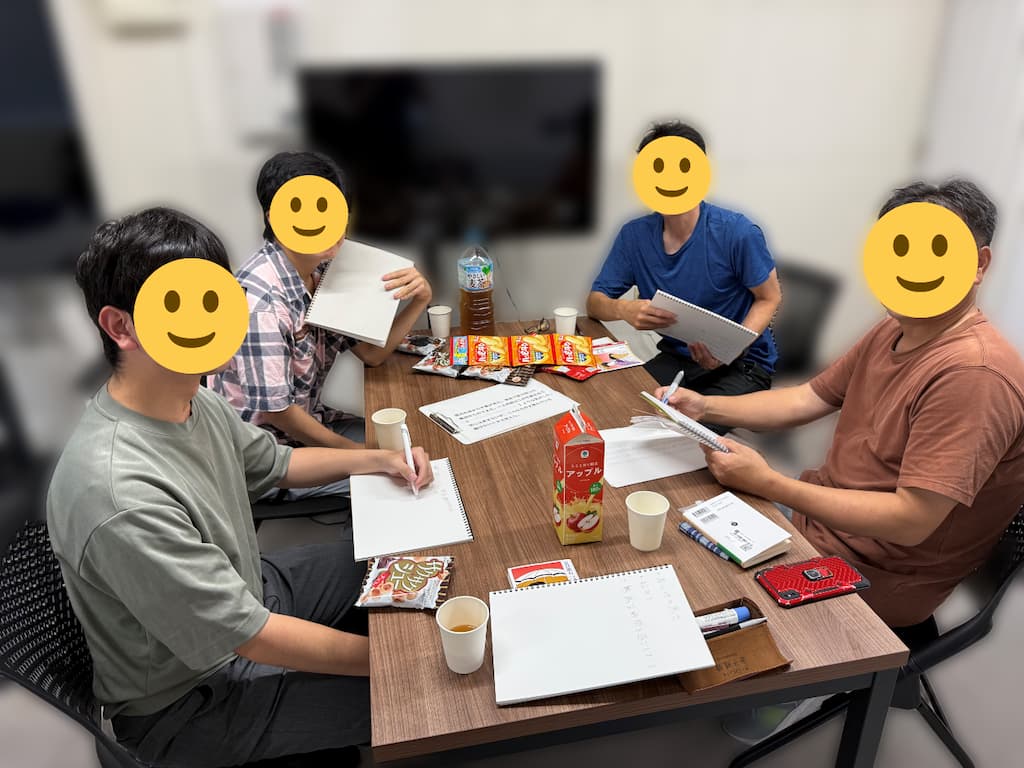第一回読書会を開催しました
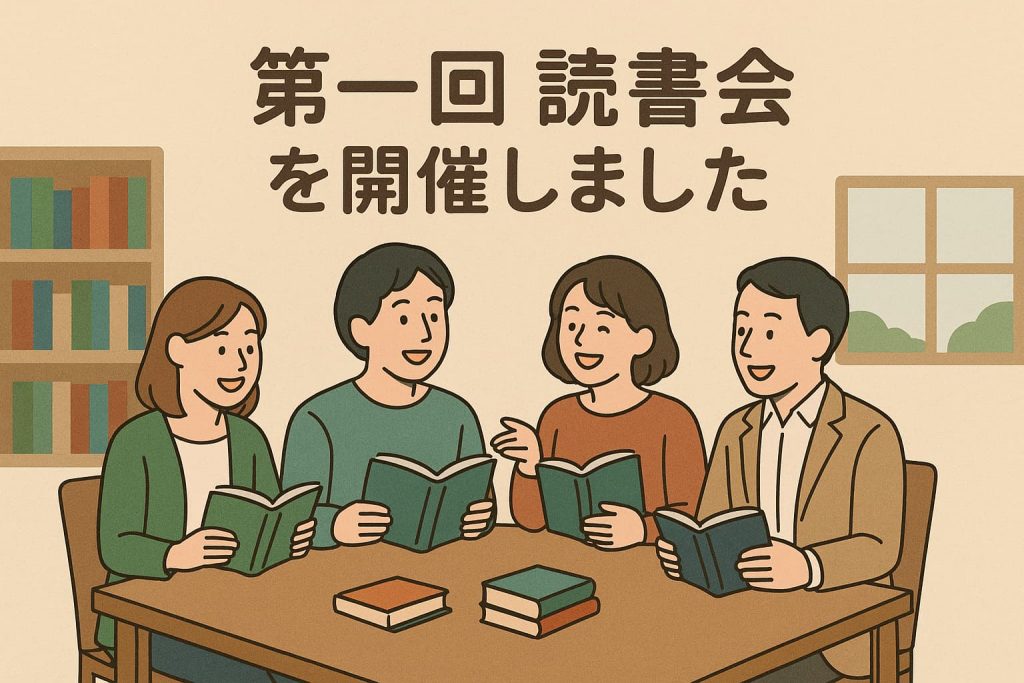
目次
読書部とは?
先日、当社の部活動支援制度を活用して、新しく「読書部」を立ち上げました!
そして記念すべき第一回読書会を開催することができました。
読書部では、主に小説(純文学寄りの名作)を皆で読んでいこうと考えています。
当社の部活動制度では、異なる5部署から合計5人以上のメンバーを集める必要があるため、自然と他部署との交流が生まれるのも魅力の一つです。
普段なかなかお話しする機会のない部署の方々とも、本を通じてつながることができそうです。
実は、読書部を立ち上げたのには、ちょっとした想いがありました。
学生時代は小説を読むのが大好きだったのですが、社会人になってからは「すぐに役に立つ本」ばかり手に取るようになっていたのです。
ビジネス書や実用書ももちろん大切ですが、どこか物足りなさを感じていました。
そんな時、ある作家さんの「すぐ役に立つことは、すぐに役に立たなくなる」という言葉が思い出され、ずっと心に引っかかっていました。
小説を読むことは確かに時間がかかるし、明日の仕事に直接役立つわけでもありません。
でも、すぐには役に立たないからこそ、きっと今後の人生においてずっと何かの足跡を残してくれるのではないか——そんな気持ちで、思い切って読書部を立ち上げることにしました。
幸い、同じような想いを持つ仲間が集まってくれて、こうして第一回目の読書会を開催することができました。
本を通じた新しい出会いと発見に、今からワクワクしています!
初回の課題図書『三四郎』
記念すべき第一回の課題図書に選んだのは、夏目漱石の『三四郎』です。
1908年に発表されたこの作品は、熊本から東京帝国大学に出てきた青年・小川三四郎の成長を描いた「前期三部作」の第一作目。
明治という時代の変化の中で、田舎から都会に出てきた若者が感じる戸惑いや憧れ、そして淡い恋心が丁寧に描かれています。
この作品は、漱石の作品の中でも比較的読みやすく、それでいて深みのある小説です。
100年以上前の作品でありながら、人の心の動きや社会との関わり方について考えさせられる部分が多く、まさに「すぐには役に立たないけれど、長く心に残る」読書体験を提供してくれる一冊だと感じました。
特に印象的なのは、主人公・三四郎の心の揺れの繊細さです。
恋心を抱きながらも一歩を踏み出せないもどかしさや、自分の未熟さに気づきつつもどう振る舞えばよいか分からない姿は、時代を超えて共感できるものがあります。
また、熊本から上京した三四郎が、都会的な人々の考え方に戸惑う場面には、「地方と都会」「伝統と近代」という社会の断層が重なっています。
社会から期待される役割と、本人の中にある不安や戸惑いのギャップ――その間で揺れる姿こそが『三四郎』の魅力であり、今を生きる私たちにも響く物語だと思います。
参加者の皆さんにとっても、久しぶりに向き合う古典文学として、ちょうど良い選択だったのではないでしょうか。
クイズ形式での発表
今回の読書会では、ちょっと変わった試みとして「クイズ形式での発表」を取り入れました。
これが想像以上に盛り上がって、本当に楽しい時間となりました!
やり方はとてもシンプルです。
参加者それぞれが『三四郎』を読んでいて「ここが印象的だった」「この表現が素敵だった」と感じた箇所を選んで、その一部分を【?】で隠し、発表するのです。
例えば「三四郎は切実に生死の問題を考えたことのない男である。考えるには、【?】すぎる。」といった具合に。
みんなでその【?】の部分に何が入るかを予想するのですが、正解するのはほぼ不可能。
でも、それがかえって面白いんです。
「正解を当てよう」というよりも「自分だったらここにどんな言葉を入れるかな?」という気持ちで自由に発想を膨らませます。
「幸せすぎる?」「若すぎる?」「苦労を知らなすぎる?」などなど、みんなの答えがバラバラで、それぞれの想像力や感性の違いが見えてとても興味深いものでした。
正解は「青春の血が、あまりに暖かすぎる」なのですが、それを発表すると「なるほど!」「そう来るか!」「それは当てられないな」と盛り上がります。
発表者が「この答えが一番良かった!」と思う回答をした人には、お菓子の小袋がプレゼントされます。
正解じゃなくても、発想が面白かったり、その場面にぴったりだったりする答えが選ばれるので、みんな真剣に、でも楽しく参加してくれました。
参加者それぞれが選んだポイントも本当に様々で、ある人は風景描写に着目し、別の人は登場人物の心情を表す部分を選び、また別の人は会話のやりとりに注目していて。
同じ本を読んでいても、心に残る箇所がこれほど違うものかと、改めて読書の奥深さを感じました。
まとめ
初回の読書会は、参加者の皆さんにとても楽しんでいただけて、正直ホッとしました。
クイズ形式での発表は初めての試みでしたが、予想以上に盛り上がり、
「思った以上に面白かった」「いろんな見方を知ることができた」といった嬉しい感想をいただきました。
普段は異なる他部署の方々と、一つの小説について語り合う時間は本当に貴重でした。
同じ本を読んでいても、それぞれ心に響く場面が違い、クイズの答えも十人十色。
その違いこそが読書会の醍醐味だと改めて実感しています。
次回は、ジョン・スタインベックの『ハツカネズミと人間』を課題図書に選びました。
今度はどんな発見や議論が生まれるのか、今からワクワクしています。
「すぐに役に立たない」読書だからこそ、きっと私たちの心の奥深くに何かを残してくれるはず。
これからも仲間と一緒に、素晴らしい本との出会いを重ねていきたいと思います。
読書部の活動を通じて、忙しい日常の中にも豊かな時間を作っていけたら、こんなに嬉しいことはありません。